目次
新電力事情を徹底解説!低圧電力と高圧電力の違いとは

電力自由化は、日本の電力市場に大きな変化をもたらしました。特に、「新電力」の参入がもたらしたインパクトは大きかったと言えます。新電力の登場により、消費者にはどのようなメリットがもたらされるのでしょうか。
今回は、新電力の概要や新電力に移行するメリットについて解説します。また、新電力の登場によって注目されるようになった「高圧電力」「低圧電力」も紹介します。新電力への切り替えや節電を検討している人は、参考にしてください。
ドコモでんきで、お得なdポイント還元を実現。お申込みはこちらから
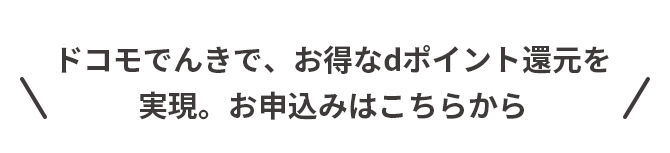
そもそも新電力とは?
そもそも「新電力」とは、どのような電力会社なのでしょうか。ここでは、新電力の概要と、新電力が登場するきっかけとなった電力自由化について詳しく解説します。
新電力の概要
新電力とは、電力市場に新規参入した「小売電気事業者」を指します。小売電気事業者とは、一般家庭に電気を供給・販売する事業者のことです。これまでは「一般電気事業者」と呼ばれ、北海道電力や東北電力、東京電力などの大手電力会社が市場を独占していましたが、昨今は「電力自由化」により、どの企業でも参入できるようになりました。
新電力の登場によって、消費者は「電気料金の節約」や「再生可能エネルギーの優先」など、自らの生活スタイルや予算に合わせて最適な小売電気事業者を選べるようになりました。
電力自由化とは?
電力自由化は、2016年4月1日に日本全国で実施された、民間企業が電力小売市場に新規参入できるようにする制度です。
以前は、地域ごとに一つの大手電力会社が電力供給を独占していました。しかし、電力自由化によって多様な民間企業が電力小売事業に参入したため、現在、消費者は自らのニーズに合った電力会社を自由に選べます。
本制度の目的は、電力市場に競争原理を導入することによるサービスの質の向上と電気料金の抑制です。消費者は、「料金プラン」「再生可能エネルギーの利用比率」「顧客サービスの質」など各社が提供するサービスを比較し、自身のライフスタイルや価値観に合った電力会社を選べます。電力自由化は、エネルギー源の多様化を促し、より持続可能な社会づくりに貢献する施策としても期待されています。
新電力に移行するメリット

電力自由化により、さまざまな企業が市場に参入できるようになりましたが、消費者にとって、大手電力会社と比較してどのようなメリットがあるのでしょう。
ここでは、新電力に移行することで得られる主なメリットについて詳しく解説します。
環境に配慮された電気を使用できる
新電力のなかには、持続可能なエネルギー源に重点を置いて事業を展開している企業が多くあります。それらの企業は、太陽光、風力、水力などの再生可能エネルギーを活用して電力を生産しており、化石燃料を使用した場合と比較して、CO2排出量が極めて少ないのが特徴です。再生エネルギーによる電力の生産は、地球温暖化の進行を抑えるのに効果的といえます。
消費者は再生可能エネルギーによる電力を選択することで、一人ひとりが環境への配慮を実践し、地球の未来に貢献できるのがメリットといえます。
電気料金を安くできる場合がある
新電力への切り替えにより、個々の消費パターンに合わせた柔軟な料金プランの選択が可能になります。
たとえば、自宅で夜間に仕事をする時間が多い人は、夜間の電気料金が割引になるプランを選ぶことで、月々の電気代を削減できるでしょう。ほかにも、「Wi-Fiとのセット割」「ポイント還元」など、新電力ならではのお得なプランが用意されている場合もあります。
ライフスタイルに合った電力消費ができる
新電力への切り替えにより、消費者はそれぞれのライフスタイルや事業活動に合わせた柔軟な電力消費計画を立てることが可能になります。
たとえば、家庭や企業ごとに電気の使用が多い時間帯は異なります。新電力のなかには、時間帯別の料金設定を提供している企業もあり、利用することで、電力コストを効果的な管理が可能です。
さらに、新電力のなかには、スマートメーターやアプリを通じてリアルタイムでの電力使用状況を把握できるサービスを提供している企業もあります。消費者は自身の電力使用パターンを視認できるため、無駄な電力消費を抑えられるでしょう。

新電力に変えるデメリットは?切り替え前に要チェック
「電力の小売全面自由化」によって電力会社や料金プランを自由に選べるようになった一方、新電力の撤退や倒産も目立っています。この記事ではその背景や「ドコモでんき」を含む新電力のデメリットについて解説します。
低圧電力と高圧電力の概要
電力供給の契約にはさまざまな形態がありますが、一般的なのが「低圧電力」もしくは「高圧電力」です。ここでは、これら二つの電力形態の違いと市場動向について解説します。
低圧電力
低圧電力は、契約電力が50kW未満の電力供給を指します。主に一般家庭や小規模の商店、飲食店、事務所などに適用され、電気製品や照明、暖房機器などに必要な電飾を提供します。
低圧電力は、電力の安定供給と効率的な使用を可能にします。また、低圧電力は設備投資が比較的少なく済むため、初期費用を抑えつつ必要な電力を確保できるというメリットも持ち合わせています。
低圧電力の市場シェア
電力自由化以降、低圧電力市場は大きな変化を遂げました。2018年9月時点で、新電力へのスイッチング件数は約1,284万件に達しており、特に三大都市圏(東京、大阪、名古屋)での切り替え率の高さが目立っています。
これは、一般家庭や小規模事業者が、従来の大手電力から新電力へと移行することで、電気料金の節約やサービスの質の向上を望んでいることを示す動きといえるでしょう。
高圧電力
高圧電力は、契約電力が50kw以上、標準電圧が6,000Vとされ、主に中小規模の商業施設、工場、病院などで利用されます。こうした施設では、機械設備や大量の照明、空調システムなど、大きな電力を必要とする機器を使用するため、高圧での電力供給が必要になります。
高圧電力の利用により、電力消費のピーク負荷を効率よくカバーし、料金を抑えることが可能です。また、高圧電力は、電力損失を最小限に抑えつつ、広範囲にわたる施設に対して、安定して電力を供給できるため、特に電力需要が連続して高い業種や施設にとっては必要な選択肢となります。
高圧電力の供給を受けるには、専用の受電設備が必要であり、適切な設計と安全対策が必須です。そのため、高圧電力を導入する際には、初期投資として設備の設置やメンテナンスの計画も重要となるため、これらのコストも考慮に入れる必要があります。
高圧電力の市場シェア
新電力が提供する高圧電力の市場シェアは、2021年をピークにして減少傾向にあります。その理由の一つが、日本電力取引所(JEPX)での電力価格の高騰です。価格の上昇は、特に高圧電力を多用する産業や商業施設にとってコスト増加を意味し、結果、新電力への切り替えが減少しています。
2021年以降、多くの地域で新電力のシェアが15%を超える水準で推移していたものの、JEPXでの価格上昇により、高圧電力の利用者が従来の電力会社に戻るケースや、エネルギー消費の削減を余儀なくされる状況が増えています。この動向は、新電力にとっても大きな挑戦と言え、価格競争力の回復やサービスの質の向上が今後の市場拡大の鍵となるでしょう。
特別高圧電力とは?
「特別高圧電力」は、標準電圧が20,000V以上とされる非常に高い電圧レベルで供給される電力で、大規模な産業施設・商業施設や大型オフィスビルなど、大量の電気を消費する施設に最適です。年間の電気代が数億円から数十億円にも及ぶこれらの施設では、電力の効率的な配分と管理が必須となります。
特別高圧電力は、その高い電圧レベルにより、電力損失を最小限に抑えながら広範囲にわたるエリアに電力を効率よく送電できることがメリットです。大規模な機械やシステムを稼働させるための安定した電力供給を確保でき、生産性の向上や運用コストの削減に寄与します。
低圧電力と高圧電力の違い

低圧電力と高圧電力は、供給方法、受電方法、料金の仕組みが異なります。ここでは、これらの違いについて詳細に解説します。
電力の供給方法が異なる
低圧電力と高圧電力では、電力の供給方法が異なります。低圧電力は、地域の電柱に設置された柱上変圧器を通じて100Vや200Vに変圧され、家庭・小規模事業所に供給されます。設備投資が比較的低コストで済むのが特徴です。
一方、高圧電力は、送電線を通じて直接6,000Vの電力が施設や工場に供給されます。専用の受電設備を設置して高圧電力を受け、必要に応じて施設内で電圧を下げる仕組みです。高圧電力は大量の電力を効率的に使用でき、大規模な産業や商業施設に適しています。
電力の受電方法が異なる
高圧電力場合は、「キュービクル」と呼ばれる専用の受電設備を設置する必要があります。キュービクルは、送電線から供給された6,000Vの高電圧を100Vや200Vに変圧するのが役割です。
一方、低圧電力では、電柱に設置された「柱上変圧器」で100Vや200Vに変圧されて各家庭・事業所に供給されるため、受電設備を設置する必要はありません。
電気料金の仕組みが異なる
電気料金の計算には、基本的に「基本料金」と「従量料金(プラス燃料費調整単価等)」の二つの要素が含まれます。低圧電力と高圧電力では、基本料金の算出方法が異なります。
低圧電力の場合は、契約容量に応じて決定するのが一般的です。
一方、高圧電力では、「実量制」と「協議制」のいずれかの方法で基本料金を決定します。それぞれについて以下で解説します。
実量制とは
実量制は、過去12か月間で最も高い電力使用量30分間の「最大需要電力(デマンド値)」をもとに、基本料金を算出する方法です。実際に使用された電力量にもとづくため、使用パターンのピーク時の電力需給を反映した料金設定となります。実量制は公平かつ合理的な算出方法であり、電力の使用効率の最大化が可能です。
協議制とは
一方、協議制では、年に一度、電力会社との間で「使用する負荷設備」や「受電設備の内容」などにもとづいて基本料金の協議が行われます。契約者のニーズに合わせたカスタマイズが可能であり、料金計画を立てやすくなります。協議制は大規模な施設や電力消費が一定の企業に適しており、長期的な財務計画に有益です。
低圧電力に切り替えるメリット・デメリット
新電力の低圧電力に切り替えることで、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。以下で解説していきます。
低圧電力に切り替えるメリット
新電力の低圧電力に切り替えることで、経済的および安全性の面でメリットがあります。まず経済的な観点では、高圧電力よりも低圧電力の方が保守点検や部品交換などのメンテナンスコストがかからないという点です。小規模事業者では、高圧電力から低圧電力に変更することで、長期的に見て運用コストを大幅に削減できるでしょう。
安全性に関しては、低圧電力の方が高圧電力に比べて波及事故のリスクが低いという点がメリットです。低圧電力システムは比較的シンプルで、事故が起きた場合にもその影響が局所的に留まるため、大きな被害につながる可能性が少なくなります。密集した住宅地や商業地区での安全性を高める上で大きなアドバンテージといえるでしょう。
低圧電力に切り替えるデメリット
低圧電力に切り替える場合、考慮すべきデメリットもあります。特に、高圧電力と比較した場合の電気料金の高さがデメリットの1つです。低圧電力は、使用量が多いほど電気料金が高くなる仕組みであり、大量に電力を消費する施設や設備での利用には不向きな場合があるでしょう。
また、低圧電力には一般的に低圧電力(動力)プランと従量電灯プランの2つにわけられます。低圧電力(動力)プランは、従量電灯プランと比較して基本料金が高く設定されているのが一般的です。そのため、月々の電力使用量が少ない家庭や小規模事業にとって、コスト効率が悪くなる可能性があるでしょう。実際の電力使用状況にもとづいてプランを選ぶことが大切です。
高圧電力に切り替えるメリット・デメリット
高圧電力への切り替えは、特に大規模施設や工場など、大量の電力を消費する場所で検討されることが多いです。ここでは、高圧電力に切り替える際のメリットとデメリットについて詳しく解説します。
高圧電力に切り替えるメリット
高圧電力に切り替えるメリットは、電気料金の単価が安くなることです。高圧電力は、発電所から直接送電される仕組みであるため、電力を変圧する必要がなく、それに伴うエネルギー損失も最小限に抑えられます。そのため、低圧電力を使用する場合に比べて電気料金の単価が安くなります。
連続的に大量の電力が必要とされる施設では、高圧電力への切り替えにより電気料金のコストを大幅に削減できます。また、高圧電力は、安定した電力供給が可能であるため、機器の稼働が停止するリスクを低減できます。
高圧電力に切り替えるデメリット
高圧電力への切り替えは多くのメリットをもたらしますが、デメリットも考慮する必要があります。最も大きな問題の一つは、初期設置費用の高さです。高圧電力システムを安全に運用するためには、受電装置であるキュービクルが必要とされ、導入する初期投資が伴います。キュービクルは高価で、設置工事も複雑です。
新しい設備を導入する際には、初期不良や予期せぬ技術的問題が発生するリスクもあります。これらの問題が発生すると、修理や部品の交換による追加コストが発生し、場合によっては運用の中断も余儀なくされる可能性があります。このようなリスクは、特に電力依存度が高い業務を行っている施設にとって大きな懸念事項です。
低圧電力から高圧電力への切り替えにかかる費用
先述したとおり、低圧電力から高圧電力に切り替える際には、キュービクルを設置する必要があります。キュービクルの費用は、必要な電力量や、施設規模によって大きく異なりますが、標準のキュービクルが200万円~500万円程度、大型のキュービクルの場合は500万円~1,000万円以上の費用が必要です。キュービクル自体の購入費用のほか、設置工事費、必要に応じた土地の整備費用などが含まれます。
さらに、高圧電力への変更後は、ランニングコストも発生します。ランニングコストには、定期的なメンテナンス費用、部品の交換費用、突発的な修理費用などが含まれ、長期的に考慮する必要があるでしょう。
まとめ
昨今では、電力自由化の導入により、多くの新電力が参入しています。新しい企業の参入により、消費者は自身のライフスタイルに合った電気料金プランを選択できます。
電力供給の契約には、一般家庭や小規模事業者などに向いている低圧電力と、中小規模の商業施設や工場、病院などに向いている高圧電力の2つがあります。電気使用量によって安くなる契約方法が異なるため、自身に合う方式を選びましょう。
「ドコモでんき」は、月々の電気料金がdポイントとして還元される「dポイントがお得にたまるドコモでんき Basic」プランをご用意しており、電気料金をお得にご利用いただけます。また、CO2排出量実質ゼロの「地球にやさしいドコモでんき Green」プランを用意しており、各々のライフスタイルによって選択が可能です。電力の安定的な供給・対応なども可能なため、あんしんしてお使いいただけます。新電力への乗り換えを検討している方は、ドコモでんきをご検討ください。
ドコモでんきで、お得なdポイント還元を実現。お申込みはこちらから
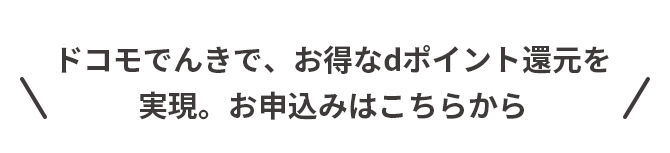
本記事の内容は公開時点の情報です。最新の情報とは異なる可能性がありますのでご注意ください。また、可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容を保証するものではありません。詳しくは 当サイトについてをご確認ください。
