目次
新電力の登場によって注目された託送料金とは?レベニューキャップ制度についても解説

新電力の登場により、電気料金の内訳に変化が生じています。これに伴い、託送料金という言葉を耳にする機会が増えたのではないでしょうか。電気料金の仕組みが複雑化し、理解が難しいと感じている人もいるかもしれません。
そこでこの記事では、託送料金の概要や電気料金の内訳の変化について解説します。レベニューキャップ制度や毎月の電気料金の決まり方についても詳しく説明するため、電気料金の仕組みを知りたい人や、料金の内訳を理解したい人は参考にしてください。
ドコモでんきで、お得なdポイント還元を実現。お申込みはこちらから
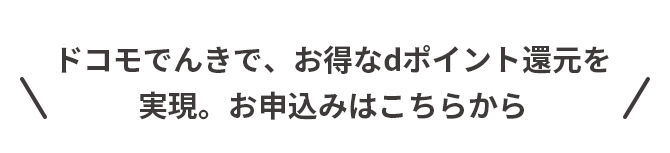
新電力の登場によって注目される託送料金とは?
電力自由化に伴い、新電力会社が市場に参入したことで、電気料金の仕組みが大きく変わりました。この変化のなかで、これまであまり知られていなかった「託送料金」という言葉が注目を集めています。しかし、その具体的な内容や私たちの生活への影響については、まだ十分に理解されていない面があるでしょう。
ここでは、託送料金の基本的な概念と、私たちの生活にどのような影響を与えるのかについて解説します。
託送料金の概要
託送料金とは、小売電気事業者が送配電事業者に支払う送配電網の利用料金のことを指しています。
電気を各家庭や企業に届けるために「電力の道路」を使用するコストと考えるとよいでしょう。具体的には、送電線や変電所などのインフラを使う際に発生する利用料です。
家庭で支払う電気料金のうち、約30〜40%がこの託送料金として充当されています。電力会社は、託送料金を使って送配電設備の維持や管理、修繕、さらには自然災害に対する防護対策を行い、安定した電力供給を保っています。
託送料金が一般家庭に与える影響
託送料金は、私たちが毎月支払う電気料金の一部です。そのため託送料金が変更されると、家計に直接的な影響をおよぼす可能性があります。
たとえば、送配電設備の更新や自然災害対策の強化などにより託送料金が上昇した場合、それに伴って電気料金も増加するでしょう。逆に、効率化や技術革新によって託送料金が引き下げられれば、電気料金の減少につながる可能性もあります。
また、各地域の送配電網の状況や維持管理にかかるコストが異なるため、託送料金は地域によって異なる場合があります。そのため、同じ電力会社のサービスを利用していても、住んでいる地域によって電気料金に差が生じることもあるでしょう。
このように、託送料金は私たちの生活に密接に関わっています。電気料金の内訳を理解し、その変動要因を知ることで、より安価で便利な電力の選択や使用につながるでしょう。
新電力の登場前後の電気料金の内訳

電力自由化により、電気料金の内訳にも大きな変化がありました。新電力会社の登場前後で、料金の設定方法や構成要素が変わっています。ここでは、その変化の詳細について解説します。電気料金の仕組みがどのように変わったのかを見ていきましょう。
新電力の登場前の内訳
新電力会社が登場する以前、電気料金は「総括原価方式」によって決定されていました。この方式では、電気供給に必要なあらゆる費用を合算し、さらに一定の利益を上乗せすることで料金が設定されます。つまり、電力供給にかかるすべてのコストが電気料金に反映されていたのです。
当時は費用の明細が表示されなかったため、消費者にとっては内訳が不透明で、何にどれだけのコストがかかっているのかわかりにくくなっていました。
総括原価方式の利点としては、安定的かつ確実に電力を供給できる点が挙げられます。電力会社は必要なコストをそのまま料金に反映できるため、設備の維持や運営が安定して行えました。しかしその一方で、コスト削減や効率化を進めるインセンティブが働きにくいという課題も存在していました。
新電力の登場後の内訳
新電力会社の参入後、電気料金の構成は大きく変わりました。現在の電気料金は、主に「電源費」と「託送料金」の2つの要素で構成されています。この変更により、料金の内訳が従来の方式より明確になりました。
電源費とは、電気を調達するためにかかったすべての費用を指します。発電所の運営費用や燃料費、電力市場から電気を購入する際の費用などが含まれます。各電力会社は、この電源費を抑えることで競争力を高めようと努力しています。
託送料金は前述のとおり、送配電網の利用料です。託送料金は依然として規制下にあり、地域の送配電事業者によって一律に決められています。そのため、新電力会社も既存の大手電力会社も、同じ託送料金を支払っています。
この新しい構成により、消費者は電気料金の内訳をより詳しく把握できるようになりました。また、電源費の部分で各社が競争することで、サービスの向上やコスト削減が進むことが期待されています。
<内訳の変化>
| 新電力登場前 | 総原価(原価+報酬)=電気料金 |
|---|---|
| 新電力登場後 | 電源費+託送料金=電気料金 |
託送料金の費用はどのくらい?

託送料金の金額は、地域によって異なるため一律ではありません。先述のとおり、送配電網の維持や管理にかかるコストが地域ごとに異なることが主な理由です。
たとえば、都市部では送配電設備が集中しており、人口密度が高いため効率よく電力を供給できますが、地方や山間部では広いエリアに電力を供給するため、設備の維持費が高くなることがあります。
託送料金の詳細な金額を知りたい場合には、住んでいるエリアの大手電力会社の料金表を確認しましょう。多くの電力会社は、自社のWebサイトで託送料金やそのほかの料金内訳を公開しているため、かかっているコストを簡単に確認できます。また、地域の電力自由化の状況によっても託送料金は変わることがあるため、新電力の参入状況も確認しておくとよいでしょう。
レベニューキャップ制度とは?
電気料金の抑制をめざす新たな取組みとして、レベニューキャップ制度が注目を集めています。この制度は、電力会社の収入に上限を設けることで、消費者の負担を軽減しようというものです。ここではレベニューキャップ制度の概要と、導入された背景について詳しく見ていきましょう。
レベニューキャップ制度の概要
レベニューキャップ制度は、2023年4月から始まった新しい仕組みです。この制度では、国が電力会社に対して「収入上限」を設定し、その範囲内で託送料金を決めるよう求めています。
電力会社は一定期間(たとえば5年間)の事業計画を作成し、事業を行うために必要となる費用(収入上限)を算出します。提出された費用を国が査定し、問題なければ収入上限を承認します。
承認後、電力会社は上限の範囲内で効率的な経営を行い、コストを抑えながらサービスの質を維持することが求められます。これにより、電力会社は無駄な支出を減らし、効率的な経営を行うインセンティブを持つことになるという仕組みです。
この制度の最大の利点は、一般家庭が負担する託送料金を抑えられる点です。電力会社の収入に上限があるため、過度な値上げを防止できます。また、電力会社が効率化を進めることで、将来的には料金の引き下げにつながる可能性もあるでしょう。
一方で、収入上限が厳しすぎると、電力会社が必要な設備投資を行えなくなる恐れもあります。安定供給と料金抑制のバランスを取ることが課題とされています。
レベニューキャップ制度が開始された背景
レベニューキャップ制度の導入には、電力業界を取り巻くさまざまな課題が背景にあります。ここでは、その主な理由について詳しく見ていきましょう。
電気業界のコスト増加が避けられない状況にあるため
電気業界では、さまざまな要因によりコストの増加が避けられない状況にあります。
まず、再生可能エネルギー電源の導入拡大に伴い、送配電網の増強が必要です。太陽光発電や風力発電などの不安定な電源を効率的に利用するためには、電力系統の強化が不可欠といえます。
また、近年増加している自然災害への対策も大きな課題です。台風や地震などの災害後、迅速に電力を復旧させるための設備投資や人員配置が求められています。さらに、老朽化した設備の更新も避けて通れません。
これらの要因により、電力会社のコストは増加傾向にあります。しかし、単純にこれらのコストを電気料金に上乗せすれば、消費者の負担が大きくなってしまいます。そのため、コスト増加を抑えつつ、必要な投資を行う方法が求められていました。
一般家庭が負担する電気料金を抑制させるため
電力会社は増加するコストに対応するため、国に託送料金の値上げを求めています。しかし、託送料金が値上げされれば、それは直接的に一般家庭の電気料金に反映されることになるでしょう。
電力自由化後も多くの家庭が従来の大手電力会社を利用し続けている現状では、託送料金の値上げは広範囲に影響をおよぼします。新電力会社を選択した家庭でも、託送料金は共通のため、影響を免れることはできません。
このような状況下で、一般家庭の負担を抑えつつ、電力会社の経営も成り立たせる方法が必要とされました。レベニューキャップ制度は、この難しい課題に対する一つの解決策として導入されたのです。
電力会社に効率的な経営を促しつつ、消費者の負担を抑えることの両立をめざすこの施策の効果に、今後も注目が集まることでしょう。
毎月支払う電気料金の決まり方についても把握しよう

家計管理を行うには、電気料金の仕組みを理解しておくことが重要です。毎月の電気料金は、複数の要素から構成されています。具体的には、基本料金、電力量料金、燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計で算出されます。これらの要素について詳しく見ていきましょう。
基本料金
基本料金は、電力会社と契約しているプランに基づいて決まる固定費用であり、電気を使用しなくても発生します。電気を使用する権利に対する費用ともいえるでしょう。
この基本料金は契約アンペア数や契約電力によって異なり、一般家庭では30アンペア・40アンペアなどの契約が多く見られます。アンペア数が大きいほど、同時に使用できる電気製品の数が増えますが、それに伴い基本料金も高くなるのが一般的です。
自身の生活スタイルに合わせて適切なアンペア数を選ぶことが、電気料金の節約につながります。たとえば一人暮らしの場合は30アンペアが一般的な選択肢となりますが、家族4人程度の世帯では40〜60アンペアが目安となるでしょう。
ただし、食洗器やドライヤーなど、電力を多く消費する機器を頻繁に使用する場合、より高いアンペア数が必要になることがあります。そのため、生活環境や使用する電気機器の種類を考慮し、最適な契約アンペア数を選ぶことが重要です。
電力量料金
電力量料金は、実際に使用した電力量に応じて計算される料金で、1kWhあたりの電力量単価と毎月の電気使用量を掛け合わせて算出されます。この電力量単価は電力会社が決定しており、プランによって異なるため、契約内容をよく確認することが大切です。
多くの電力会社では、消費電力量に応じて料金単価が異なる3段階の料金制度を導入しています。一定の使用量までは比較的安い単価が適用され、使用量が増えるにつれて単価が上がっていく仕組みです。この料金制度により、節電を促進する効果が期待されています。
たとえば、1〜120kWhまでは1kWhあたり20円、121〜300kWhまでは25円、301kWh以上は30円といった具合です。そのため、使用量を抑えることで、より安い単価で電気を利用できるようになります。
また、季節や時間帯によって単価が変わるプランも存在します。自身の生活パターンに合わせて選択することで、さらなる節約が可能となるでしょう。消費者は電気の使用状況を見直し、賢くプランを選ぶことが大切です。
燃料費調整額
燃料費調整額は、火力発電を稼働させるために必要な燃料の価格変動を電気料金に反映させた費用です。これにより、世界経済の変化や国際的なエネルギー市場の動向に応じて、電気料金が適切に調整される仕組みになっています。
燃料費調整額は、原油や液化天然ガス(LNG)、石炭などの価格変動に基づいて毎月算定されます。これらの燃料の市場価格が上昇すれば、調整額もプラスとなり、結果として電気料金が増加することになるでしょう。逆に、燃料価格が下落すれば調整額はマイナスとなり、電気料金が減少するという特徴があります。
燃料費調整額があることで、燃料価格の変動リスクを電力会社と消費者の間で分担できます。たとえば急激な燃料価格の上昇があった場合でも、電力会社の経営を安定させつつ、消費者への影響を緩和できるのです。これにより、電力会社は安定した供給を維持しながら、消費者もある程度予測可能な料金で電気を利用できるようになります。
ただし、長期的な燃料価格の上昇傾向は、再生可能エネルギーへの移行を加速させる要因にもなっています。消費者はこの制度を理解し、燃料価格の動向に注意を払うことが重要です。
再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギーの普及を促進するための費用を、電気の使用者が負担する制度です。太陽光や風力などの再生可能エネルギーで発電した電力を電力会社が固定価格で買い取る際、費用の一部を消費者が賄います。
この賦課金は、使用した電力量に応じて計算されます。単価は年度ごとに見直されていますが、再生可能エネルギーの導入が進んでいることが反映され、徐々に上昇傾向にあります。
一見すると負担が増えるように思えますが、この制度には再生可能エネルギーの普及による地球温暖化対策や環境保護、エネルギー自給率の向上につながるという意義があります。長期的には化石燃料への依存度を下げ、安定した電力供給につながることが期待されています。
こうしたさまざまな要素が組み合わさって、私たちが毎月支払う電気料金が決まっています。これらの仕組みを理解することで、より賢明な電力の使用や、適切なプラン選択ができるようになるでしょう。
まとめ

電力自由化に伴い、電気料金の仕組みが大きく変わりました。新たに注目されている託送料金は、送配電網の利用料として電気料金の一部を構成しています。また、レベニューキャップ制度の導入により、電力会社の収入に上限が設けられ、料金の抑制が図られました。
毎月の電気料金は、基本料金、電力量料金、燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金から成り立っています。これらの要素を理解することで、自身の生活スタイルに合わせた適切なプラン選択や節電対策ができるでしょう。電気料金の仕組みを知ることは、家計管理の観点からも重要です。
毎月の電気料金を賢く支払いたい方には、dポイントがお得にたまる新電力「ドコモでんき」がおすすめです。電気代ごとにdポイントがザクザクたまるドコモでんき Basic、CO2フリーの再生可能エネルギーを活用した地球にやさしいドコモでんき Greenからプランを選んで利用できます。電気の品質を変えずお得に使いたい方はぜひドコモでんきをご検討ください。
ドコモでんきで、お得なdポイント還元を実現。お申込みはこちらから
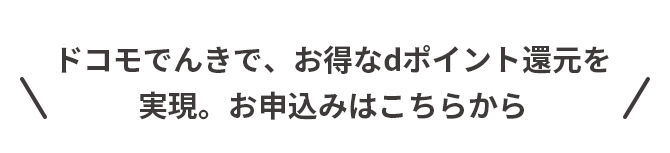
本記事の内容は公開時点の情報です。最新の情報とは異なる可能性がありますのでご注意ください。また、可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容を保証するものではありません。詳しくは 当サイトについてをご確認ください。
